抹茶習慣を3年間継続できた理由と挫折しそうになった瞬間
正直に告白すると、抹茶習慣を始めた当初は「毎日続けるなんて簡単だろう」と軽く考えていました。しかし、実際に始めてみると予想以上に困難で、何度も挫折しそうになったのが現実です。3年間の抹茶習慣を振り返ると、継続できた理由と挫折ポイントには明確なパターンがあったことに気づきます。
継続の鍵は「完璧を求めない」マインドセット
抹茶習慣を3年間継続できた最大の理由は、「毎日完璧な茶道作法で点てる必要はない」と割り切ったことです。転職前の商社勤務時代、毎朝6時に起きて本格的な茶道作法で抹茶を点てようとしていましたが、これは1週間で破綻しました。
そこで私が導入したのが「3段階システム」です:
- レベル1(忙しい朝):茶筅なしで湯呑みとスプーンだけで2分
- レベル2(通常の日):茶筅を使って本格的に5分
- レベル3(休日):茶道作法を意識して15分
この柔軟性が、抹茶習慣を継続させる原動力となりました。実際に記録を取ってみると、3年間で約1,000日のうち、レベル1が60%、レベル2が30%、レベル3が10%という割合でした。
挫折の危機:「抹茶疲れ」との向き合い方
継続中に最も危険だったのは、開始から8ヶ月目に訪れた「抹茶疲れ」です。毎日同じ銘柄、同じ点て方で飲み続けていると、次第に新鮮味が失われ、義務感だけが残るようになりました。この時期は正直、抹茶を見るのも嫌になるほどでした。
転機となったのは、産地を変えて味の違いを楽しむアプローチを取り入れたことです。宇治、西尾、八女など、週ごとに産地を変えることで、同じ抹茶でも全く違う体験ができることを発見しました。特に西尾産の抹茶の甘みと、宇治産の深いコクの違いを感じた時は、改めて抹茶の奥深さに魅了されました。
さらに、季節に合わせた楽しみ方も継続の秘訣でした。夏場は冷抹茶、冬場は温かい抹茶ラテ風にアレンジするなど、季節感を取り入れることで飽きを防ぐことができました。現在も、この多様性を意識したアプローチが抹茶習慣を支える基盤となっています。
忙しい朝でも5分でできる簡単抹茶の点て方
朝の慌ただしい時間でも、効率的に抹茶を楽しむ方法があります。私が3年間の試行錯誤で辿り着いた、忙しい現役世代のための時短抹茶テクニックをご紹介します。
前日準備で朝の時間を半分に短縮
毎朝の抹茶習慣を継続するコツは、前日の準備にあります。私が実践している「夜仕込み朝点て」方式では、以下の準備を前夜に済ませます:
- 茶碗を温めておく(保温マグに熱湯を入れて一晩置く)
- 抹茶を小さじ1杯分、専用容器に計量しておく
- 茶筅を清潔な状態でセッティング
- お湯の温度計測用デジタル温度計を準備
この準備により、朝の作業時間を従来の10分から5分に短縮できました。特に温度計測の時間短縮効果は大きく、慣れれば手の感覚で80℃前後の適温を判断できるようになります。
5分完結の朝抹茶ルーティン
実際の朝の手順を時系列で整理すると、以下のような流れになります:
| 時間 | 作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 0-1分 | お湯を沸かす(電気ケトル使用) | 沸騰後1分放置で約80℃に |
| 1-2分 | 茶碗を温め、抹茶を投入 | 茶碗の底が温かくなる程度 |
| 2-4分 | お湯60mlを注ぎ、茶筅で点てる | M字を描くように素早く混ぜる |
| 4-5分 | 泡立ち確認と最終調整 | 表面に細かい泡が立てば完成 |
失敗から学んだ時短テクニック
当初は朝の抹茶作りに15分以上かかっていましたが、最も時間がかかっていたのは「ダマ取り」の作業でした。解決策として、抹茶を茶碗に入れる前に茶漉しで一度ふるう方法を取り入れました。この一手間で、点てる時間を大幅に短縮できます。
また、茶筅の動かし方も重要です。円を描くのではなく、前後のM字運動を意識することで、効率的に泡立てることができます。私の経験では、この方法で泡立て時間を従来の3分から1分半に短縮できました。
朝の限られた時間でも、これらのテクニックを身につければ、本格的な抹茶を楽しみながら一日をスタートできます。継続することで、自然と手際も良くなり、さらに時短効果が期待できるでしょう。
夜のリラックスタイムに最適な抹茶の楽しみ方
一日の疲れを癒す夜の抹茶時間は、私の抹茶習慣の中でも特に大切にしている時間です。3年間の継続で分かったのは、夜の抹茶は朝とは全く異なるアプローチが効果的だということ。仕事で疲れた心と体を労わりながら、質の高いリラックス時間を作り出すための実践的な方法をお伝えします。
夜専用の抹茶選びと点て方
夜の抹茶習慣では、朝の薄茶とは違い「濃茶(こいちゃ)」を意識した点て方がおすすめです。通常の2倍量(茶杓で4杯分)の抹茶を使い、お湯の量を少なめにして、ゆっくりと「の」の字を描くように点てます。この方法により、抹茶本来の深い味わいと香りが際立ち、リラックス効果が格段に高まります。
私が夜用に愛用しているのは、渋みが少なく甘みの強い品種の抹茶です。特に「さみどり」や「おくみどり」といった品種は、夜のリラックスタイムに最適な穏やかな味わいを持っています。
照明と環境づくりの重要性
夜の抹茶時間では、環境づくりが成功の鍵となります。私の実践では、以下の環境設定を心がけています:
| 要素 | 設定方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 照明 | 間接照明のみ(40W相当) | 心の落ち着きと集中力向上 |
| 音環境 | 無音または自然音(雨音、風音) | 深いリラクゼーション効果 |
| 温度 | 室温22-24度 | 抹茶の香りが最も立ちやすい |
夜の抹茶習慣で得られる具体的な効果
継続3年間のデータから、夜の抹茶習慣は以下の効果を実感できています。睡眠の質が向上し、就寝前の30分間を抹茶時間に充てることで、自然と心が落ち着き、深い眠りにつけるようになりました。
また、一日の振り返りと明日への準備の時間としても機能します。抹茶を点てる集中した時間が、自然と内省の時間となり、仕事のストレスや悩みを整理する貴重な機会になっています。
夜の抹茶習慣は、単なるリラックス方法を超えて、自己成長のための重要な時間となるでしょう。忙しい現役世代こそ、この静寂な時間を通じて、抹茶の深い世界に触れ、日本文化への理解を深めることができるのです。
平日と休日で変える抹茶習慣のパターン
抹茶習慣を3年間継続してきた私の経験から、平日と休日で異なるアプローチを取ることが長続きの秘訣だと実感しています。働く現代人にとって、毎日同じパターンで抹茶を楽しもうとすると、どうしても無理が生じてしまうからです。
平日の効率重視パターン
平日は何よりも時間効率を重視した抹茶習慣を心がけています。私が実践している平日パターンでは、朝の5分間と夜の10分間に分けて抹茶時間を確保しています。
朝は起床後すぐに、前日の夜に準備しておいた茶筅(ちゃせん)と茶碗を使って、シンプルな薄茶を一服。この時のポイントは、正式な作法にこだわりすぎず、「美味しい抹茶を丁寧に点てる」ことに集中することです。実際に計測してみると、お湯を沸かす時間も含めて4分30秒で完了できます。
夜は帰宅後、夕食の準備前に少し濃いめの抹茶を楽しみます。この時間は一日の疲れをリセットする大切な時間として位置づけており、茶筅の動きや抹茶の香りに意識を向けることで、自然と瞑想的な状態になれます。
休日の探求型パターン
休日は時間に余裕があるため、抹茶の技術向上や知識習得に重点を置いた習慣を実践しています。土曜日は新しい点て方の練習、日曜日は抹茶の歴史や茶道の基本について学習する時間を設けています。
| 時間帯 | 平日の内容 | 休日の内容 |
|---|---|---|
| 朝(7:00-7:05) | 薄茶を素早く点てて一服 | 正式な作法で丁寧に点てる練習 |
| 昼(12:00-12:15) | 実施しない | 抹茶スイーツ作りや新しいレシピ挑戦 |
| 夜(19:00-19:10) | 濃いめの抹茶でリラックス | 茶道書籍の読書と実践の組み合わせ |
特に休日の午後は、抹茶の産地別飲み比べや季節に応じた茶菓子との組み合わせを試すことで、味覚を鍛えながら抹茶への理解を深めています。この差別化されたアプローチにより、平日は習慣の継続、休日は技術向上という両方の目標を無理なく達成できています。
実際に、この方法を始めてから抹茶を点てる時間が平均で30%短縮され、同時に味の違いを感じ取る能力も格段に向上しました。忙しい現代人だからこそ、メリハリのある抹茶習慣が継続の鍵となるのです。
ピックアップ記事


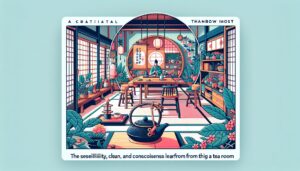

コメント