茶農家での衝撃的な発見:同じ茶葉から抹茶と緑茶が生まれる瞬間を目撃
静岡県の茶農家で体験学習をしていた時、私は茶葉の世界に対する認識を根本から覆される瞬間に立ち会いました。その日の朝、農家の田中さん(仮名)が私に見せてくれたのは、まだ若々しい緑色をした同じ茶の木から摘まれた茶葉でした。
「翔太さん、この茶葉がどうやって抹茶と緑茶に分かれるか、実際に見てみませんか?」
その言葉に導かれて工場に入ると、そこには私の想像を超えた光景が広がっていました。
製造工程の分岐点で見た決定的な違い
同じ茶葉から始まる製造工程でしたが、抹茶緑茶違いの最も重要なポイントは、摘採前の栽培方法にありました。抹茶用の茶葉は「覆い下栽培」という方法で、摘採の約20日前から黒い覆いで茶園全体を覆います。一方、緑茶用の茶葉は太陽の光を直接浴びて育てられます。
実際に覆いの下に入ってみると、薄暗い環境の中で茶葉が静かに成長している様子を観察できました。この光を遮断する栽培方法により、茶葉中のテアニン(うま味成分)が増加し、カテキン(渋味成分)の生成が抑制されるのです。
石臼挽きの瞬間に感じた抹茶の本質
製造工程で最も印象的だったのは、石臼で茶葉を挽く作業でした。覆い下栽培で育てられた茶葉は、蒸した後に揉まずに乾燥させ「碾茶(てんちゃ)」となります。この碾茶を石臼でゆっくりと挽く過程で、あの鮮やかな緑色の抹茶パウダーが生まれるのです。
石臼の回転速度は1分間に約60回転という驚くほどゆっくりとしたペースで、1時間でわずか40グラムしか挽けません。この時間をかけた製法により、摩擦熱による品質劣化を防ぎ、抹茶特有の深い香りと鮮やかな色を保持できるのです。
対照的に、緑茶は摘採後すぐに蒸し、揉み、乾燥させるという工程を経て茶葉の形状を保ったまま仕上げられます。この製法の違いが、最終的な味わいや用途の違いを生み出していることを、実際の製造現場で体感できたのは貴重な経験でした。
抹茶と緑茶の違いを製造工程から徹底解説
製造工程で決まる抹茶と緑茶の根本的な違い
静岡の茶農家で実際に製造工程を見学した際、抹茶と緑茶の違いを目の当たりにして衝撃を受けました。同じ茶葉から作られるにも関わらず、製造工程の違いによって全く異なる特性を持つ茶になるのです。
栽培段階での決定的な違いは、抹茶の原料となるてん茶の栽培では、摘み取り前の約20日間、茶畑全体を覆いで遮光することです。この「覆い下栽培」により、茶葉は直射日光を避けて育ちます。一方、緑茶は最後まで日光を浴びて栽培されます。
| 工程 | 抹茶(てん茶) | 緑茶(煎茶) |
|---|---|---|
| 栽培 | 20日間の遮光栽培 | 日光下で栽培 |
| 蒸し | 短時間蒸し | 中蒸し~深蒸し |
| 揉み | 揉まない | 複数回の揉み工程 |
| 乾燥 | 炉で乾燥 | 火入れ乾燥 |
| 最終工程 | 石臼で挽いて粉末化 | 茶葉のまま仕上げ |
製造工程が生み出す成分と味の違い
農家の方から教わった重要なポイントは、遮光栽培により茶葉のテアニン(うま味成分)が増加し、カテキン(渋み成分)の生成が抑制されることです。これが抹茶特有の深いうま味と甘みを生み出します。
実際に製造工程を見学して分かったのは、抹茶緑茶違いの最大のポイントは「揉み工程の有無」です。緑茶は揉むことで茶葉の細胞を破壊し、成分を抽出しやすくしますが、抹茶の原料となるてん茶は一切揉まずに乾燥させます。
さらに、抹茶は茶葉全体を粉末にして摂取するため、水溶性・脂溶性両方の栄養成分を丸ごと摂取できます。緑茶は抽出液のみを飲むため、主に水溶性成分のみの摂取となります。
忙しい現役世代の方にとって、この製造工程の違いを理解することで、用途に応じた使い分けが可能になります。集中力を高めたい時は抹茶、リラックスしたい時は緑茶といった具合に、製造工程から生まれる特性を活かした選択ができるようになるでしょう。
茶畑で学んだ栽培方法の決定的な違い
私が静岡の茶農家で研修を受けた際に最も驚いたのは、抹茶と緑茶の栽培方法における決定的な違いでした。同じ茶の木から作られるにも関わらず、収穫前の管理方法が全く異なることで、抹茶緑茶違いが生まれる根本的な理由を実際に目の当たりにしたのです。
遮光栽培が生み出す抹茶の特別な性質
抹茶の原料となる碾茶(てんちゃ)は、収穫前の約20日間、茶畑全体を黒い覆いで遮光する「覆下栽培(おおいしたさいばい)」という特殊な方法で育てられます。私が訪れた茶畑では、5月上旬に巨大な黒いネットが茶畑一面に張られ、まるで夜のような暗闇の中で茶葉が育っていました。
この遮光により、茶葉は太陽光を求めて葉緑素を増やし、同時に渋味成分のカテキンが減少します。農家の方に教えていただいたのは、「光を遮ることで、茶葉は必死に光合成をしようとして、うま味成分のテアニンを蓄積する」という仕組みです。実際に遮光中の茶葉を触らせていただくと、普通の緑茶用の茶葉よりも明らかに柔らかく、色も深い緑色をしていました。
緑茶の露地栽培との比較
一方、緑茶は太陽の光を十分に浴びせる露地栽培で育てられます。同じ茶畑で比較観察した結果、以下のような違いが明確に現れていました:
| 栽培方法 | 光の条件 | 茶葉の特徴 | 主要成分 |
|---|---|---|---|
| 抹茶(覆下栽培) | 収穫前20日間遮光 | 濃緑色、柔らかい | テアニン豊富、カテキン少 |
| 緑茶(露地栽培) | 十分な日光 | 黄緑色、しっかり | カテキン豊富、渋味強 |
農家の方から「遮光栽培は手間もコストも3倍かかる」と伺いましたが、この特別な栽培方法こそが抹茶独特の甘味と深い色合いを生み出す秘密だったのです。実際に収穫直前の茶葉を味見させていただくと、遮光栽培の茶葉は青臭さが少なく、自然な甘味を感じることができました。
この栽培段階での違いを理解することで、抹茶と緑茶それぞれの特性を活かした楽しみ方が見えてきます。忙しい現代人にとって、短時間でこうした本質的な違いを学べる茶農家体験は、抹茶への理解を深める最も効率的な方法の一つだと実感しています。
石臼挽きと機械製茶:製造現場で見た工程の差
静岡の茶農家を訪れた際、最も印象深かったのは抹茶と緑茶の製造現場を同時に見学できたことでした。同じ茶葉から始まりながら、全く異なる製造工程を辿る様子は、抹茶緑茶違いを理解する上で非常に貴重な体験となりました。
伝統的な石臼挽きの現場
抹茶製造で最も感動したのは、石臼挽きの工程です。碾茶(てんちゃ)を石臼で挽く作業は、まさに職人技の世界でした。農家の方によると、1時間でわずか40gしか挽けないそうです。実際に石臼の回転音を聞いていると、ゆっくりとした一定のリズムで、まるで時間が止まったような感覚になります。
石臼の回転速度は毎分60回転程度と非常にゆっくりで、これは摩擦熱を避けるためです。熱が加わると抹茶の風味が損なわれるため、この低速回転が不可欠なのです。挽きたての抹茶を味見させていただいたとき、その鮮やかな緑色と濃厚な旨味に驚きました。
機械製茶の効率性
一方、緑茶の製造現場では機械化が進んでいました。蒸し工程では大型の蒸し機で一度に大量の茶葉を処理し、揉捻機(じゅうねんき)で茶葉を揉み、乾燥機で仕上げる流れです。1日で数百キロの茶葉を処理できる効率性は圧倒的でした。
特に印象的だったのは、緑茶製造では茶葉の形状を保ちながら水分を飛ばす技術です。機械の設定温度は80-90度で管理され、茶葉の色と香りを最適化していました。
品質への影響
製造工程の違いが最終的な品質に与える影響は顕著です。石臼挽きの抹茶は粒子が非常に細かく(平均粒径10ミクロン以下)、舌触りが滑らかでした。対して機械製茶の緑茶は、茶葉の繊維質が残るため、お湯で抽出する際の香りの立ち方が異なります。
農家の方は「抹茶は粉末にすることで茶葉の栄養を丸ごと摂取できるが、緑茶は抽出液を楽しむもの」と説明してくださいました。この製造現場での学びは、普段の抹茶選びにも活かされており、石臼挽きの表示を必ず確認するようになりました。
ピックアップ記事

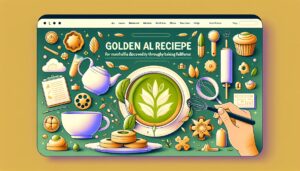
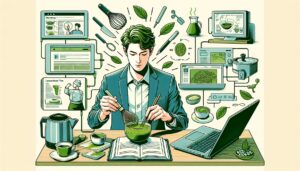

コメント